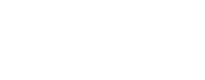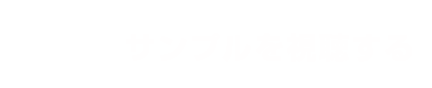なぜ、MRI検査を紹介して信頼を得る獣医師と信頼を失う獣医師がいるのか?
※なぜ、ホームドクターに「MRIの知識」が必要なのか?
先生は、「MRIは、専門医だけが学べばいい」と思っていませんか?
確かにMRIは、検査機器の導入コストが億単位にのぼるうえ、撮影にも読影にも高度な知識が求められます。そのため、「一次診療には関係がない」とお考えのドクターもいらっしゃいます。
しかし、MRIの得意分野である神経疾患では、診断・治療のタイミングが、たった数日の差で予後に大きく影響するケースがあるのを、ご存じでしょうか?
事実、「紹介の判断が遅れたことで、生命を落としてしまった」症例も少なくありません。MRIの検査費用は、他の線検査に比べると高額なため、ご家族に勧めにくいと感じるかもしれません。
しかし、尊い生命が失われたあとに、「あのとき、紹介していれば…」と後悔しても、もう遅いのです。
だからこそ、ホームドクターには、MRI検査が必要な症例のご家族に正しく提案する知識が求められるのです。
※治療介入が遅れたチワワのお話
ある日、都内の小さな動物病院に、けいれん発作を起こした2歳のチワワが来院しました。診察時にはすでに発作はおさまり、意識もハッキリ。体温も平熱、血液検査も大きな異常はありません。
ドクターは、「とりあえず、今は様子を見ましょうか」とご家族に伝え、抗てんかん薬とプレドニゾロンを処方しました。
以降、内服が途切れると症状が再発してしまうため、ドクターは薬を処方し続けていました。一ヶ月ほどは落ちついていたものの、再び発作が発生し、ご家族が慌てて来院します。
今回は、前回よりも明らかに発作の時間が長く、左旋回と斜頚もみられました。「これは神経の異常かもしれない」と考えたドクターは、二次診療施設への紹介を決断します。
MRI検査の結果、チワワの脳には元に戻らない複数の病変が確認されました。すぐに治療は開始されましたが、重度の後遺症が残ってしまいました。
本当に残念なお話ですが、「紹介判断の遅れ」が、取り返しのつかない結果を招いてしまったのです。このようなケースは、決して珍しくありませんが…
※MRIを紹介すべきか悩んだ経験はありませんか?
MRI検査は、動物の予後を大きく左右することもある重要な検査です。しかし、それには「適切なタイミング」で検査する必要があります。
神経疾患なのかわからずに様子を見てしまうと、症状が進行し、MRIがリスクの高い検査になってしまう可能性もあるのです。
だからこそ、ホームドクターには「どんな症例にMRI検査が必要なのか?」「MRI検査で何がわかるのか?」といった基礎的な知識が求められます。
また、MRI検査が必要な神経病好発疾患はある程度限られており、これを知ることで、紹介すべき症例の見落としは大きく減らせます。
この動画セミナーでは、3,000件を超えるMRI検査をおこなってきたスペシャリスト・小山英志先生が、現場で「迷わず紹介できるようになる指標」を、豊富な症例とともにわかりやすく解説。
動画セミナー視聴後、先生も、MRI検査を必要とする症例のご家族に対し、自信を持って検査をおすすめできるようになるはずです。
「もっと早く知っていれば…」と後悔する前に、適切なMRI検査への第一歩を踏み出しませんか?
- MRIの重要性がわかる犬の症例
- MRI検査を理解する「2つのポイント」
- MRI検査における麻酔の目的とは?
- 麻酔前の確認事項とは?
- 急性の後肢不全麻痺を生じた犬の症例
- 知性、行動の評価のポイント
- 麻酔リスクが高い場合の対処法
- MRI検査の「珍しい危険性」とは?
- MRI検査でよくある勘違いとは?
- MRI検査で、確定診断はできるのか?
- 神経症状の異常は、必ずMRIで発見できるのか?
- なぜ、臨床医にMRIの知識が必要なのか?
- 臨床医はMRIの何を見るべきなのか?
- 臨床家が知っておくべきMRI検査での重要な所見
- 3種類の脳ヘルニアと、その特徴
- MRI検査をすべきか悩む状況
- 特発性てんかんに、MRI検査は必要か?
- 忘れられがちな重要な疾患とは?
- 迷わずMRI検査をすべき脊髄のパターン
- 犬の脳腫瘍は、何が多いのか?
- 複数回のてんかん発作がみられた犬の症例
- 慢性の四肢不全麻痺の犬の症例
- 犬の脳炎は、MRIでどこまでわかるのか?
- 典型的なFIPのMRI
- 典型的な椎間板ヘルニアとMRI検査

※ご購入後すぐに、このページで本編をご視聴いただけます
- 教材内容
- 4セクション(合計177分収録)
- 特典
-
・ レジュメデータ
・ 特典データ - Sec1: MRI検査での麻酔(31分)
- なぜ、MRI検査への苦手意識があるのか?/ MRI検査における麻酔を理解しよう
- Sec2: MRI検査でわかる事わからない事(31分)
- よくある勘違い/ 臨床医が知っておくべき知識
- Sec3: MRIを撮るべきパターン(49分)
- よくあるパターン/ MRIを撮るべきパターン(脊髄)
- Sec4: 典型症例(66分)
- 犬に多い脳腫瘍/MRI検査/典型症例:脊髄/犬猫に多い脊髄/脊椎腫瘍
講師:小山 英志
岩手大学農学部獣医学科卒業後、一般動物病院勤務。その後、CTとMRI専門の病院である「動物検診センターキャミック」で年間200件以上のMRI検査をおこなう。2018年より、宮城県仙台市の「総合どうぶつ病院」勤務。画像診断だけでなく神経疾患の診療にも精通する稀有なドクターであり、これまで3,000件以上のMRI検査を担当している。

なぜ、MRI検査を紹介して信頼を得る獣医師と信頼を失う獣医師がいるのか?
※なぜ、ホームドクターに「MRIの知識」が必要なのか?
先生は、「MRIは、専門医だけが学べばいい」と思っていませんか?
確かにMRIは、検査機器の導入コストが億単位にのぼるうえ、撮影にも読影にも高度な知識が求められます。そのため、「一次診療には関係がない」とお考えのドクターもいらっしゃいます。
しかし、MRIの得意分野である神経疾患では、診断・治療のタイミングが、たった数日の差で予後に大きく影響するケースがあるのを、ご存じでしょうか?
事実、「紹介の判断が遅れたことで、生命を落としてしまった」症例も少なくありません。MRIの検査費用は、他の線検査に比べると高額なため、ご家族に勧めにくいと感じるかもしれません。
しかし、尊い生命が失われたあとに、「あのとき、紹介していれば…」と後悔しても、もう遅いのです。
だからこそ、ホームドクターには、MRI検査が必要な症例のご家族に正しく提案する知識が求められるのです。
※治療介入が遅れたチワワのお話
ある日、都内の小さな動物病院に、けいれん発作を起こした2歳のチワワが来院しました。診察時にはすでに発作はおさまり、意識もハッキリ。体温も平熱、血液検査も大きな異常はありません。
ドクターは、「とりあえず、今は様子を見ましょうか」とご家族に伝え、抗てんかん薬とプレドニゾロンを処方しました。
以降、内服が途切れると症状が再発してしまうため、ドクターは薬を処方し続けていました。一ヶ月ほどは落ちついていたものの、再び発作が発生し、ご家族が慌てて来院します。
今回は、前回よりも明らかに発作の時間が長く、左旋回と斜頚もみられました。「これは神経の異常かもしれない」と考えたドクターは、二次診療施設への紹介を決断します。
MRI検査の結果、チワワの脳には元に戻らない複数の病変が確認されました。すぐに治療は開始されましたが、重度の後遺症が残ってしまいました。
本当に残念なお話ですが、「紹介判断の遅れ」が、取り返しのつかない結果を招いてしまったのです。このようなケースは、決して珍しくありませんが…
※MRIを紹介すべきか悩んだ経験はありませんか?
MRI検査は、動物の予後を大きく左右することもある重要な検査です。しかし、それには「適切なタイミング」で検査する必要があります。
神経疾患なのかわからずに様子を見てしまうと、症状が進行し、MRIがリスクの高い検査になってしまう可能性もあるのです。
だからこそ、ホームドクターには「どんな症例にMRI検査が必要なのか?」「MRI検査で何がわかるのか?」といった基礎的な知識が求められます。
また、MRI検査が必要な神経病好発疾患はある程度限られており、これを知ることで、紹介すべき症例の見落としは大きく減らせます。
この動画セミナーでは、3,000件を超えるMRI検査をおこなってきたスペシャリスト・小山英志先生が、現場で「迷わず紹介できるようになる指標」を、豊富な症例とともにわかりやすく解説。
動画セミナー視聴後、先生も、MRI検査を必要とする症例のご家族に対し、自信を持って検査をおすすめできるようになるはずです。
「もっと早く知っていれば…」と後悔する前に、適切なMRI検査への第一歩を踏み出しませんか?
- MRIの重要性がわかる犬の症例
- MRI検査を理解する「2つのポイント」
- MRI検査における麻酔の目的とは?
- 麻酔前の確認事項とは?
- 急性の後肢不全麻痺を生じた犬の症例
- 知性、行動の評価のポイント
- 麻酔リスクが高い場合の対処法
- MRI検査の「珍しい危険性」とは?
- MRI検査でよくある勘違いとは?
- MRI検査で、確定診断はできるのか?
- 神経症状の異常は、必ずMRIで発見できるのか?
- なぜ、臨床医にMRIの知識が必要なのか?
- 臨床医はMRIの何を見るべきなのか?
- 臨床家が知っておくべきMRI検査での重要な所見
- 3種類の脳ヘルニアと、その特徴
- MRI検査をすべきか悩む状況
- 特発性てんかんに、MRI検査は必要か?
- 忘れられがちな重要な疾患とは?
- 迷わずMRI検査をすべき脊髄のパターン
- 犬の脳腫瘍は、何が多いのか?
- 複数回のてんかん発作がみられた犬の症例
- 慢性の四肢不全麻痺の犬の症例
- 犬の脳炎は、MRIでどこまでわかるのか?
- 典型的なFIPのMRI
- 典型的な椎間板ヘルニアとMRI検査
講師:小山 英志
岩手大学農学部獣医学科卒業後、一般動物病院勤務。その後、CTとMRI専門の病院である「動物検診センターキャミック」で年間200件以上のMRI検査をおこなう。2018年より、宮城県仙台市の「総合どうぶつ病院」勤務。画像診断だけでなく神経疾患の診療にも精通する稀有なドクターであり、これまで3,000件以上のMRI検査を担当している。
- 収録内訳
- 4セクション(合計177分収録)
- 特典
- レジュメデータ ・ 特典データ
- Sec1:MRI検査での麻酔(31分)
- なぜ、MRI検査への苦手意識があるのか?/ MRI検査における麻酔を理解しよう
- Sec2:MRI検査でわかる事わからない事(31分)
- よくある勘違い/ 臨床医が知っておくべき知識
- Sec3:MRIを撮るべきパターン(49分)
- よくあるパターン/ MRIを撮るべきパターン(脊髄)
- Sec4:典型症例(66分)
- 犬に多い脳腫瘍/MRI検査/典型症例:脊髄/犬猫に多い脊髄/脊椎腫瘍